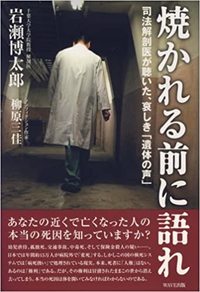犯行の痕跡ない殺害遺体、鑑識係はどう見抜くのか
変死体に向き合う鑑識係が現場から訴える「危機感」
2020.12.29(火)
大阪府警の所轄警察署の鑑識係として約4000体の『変死体』と向き合ってきた著者・村上和郎氏は、「遺体は凶器と並ぶ証拠の要だ」と言う。しかし、「それだけに誤認検視のリスクを危惧している」とも……。今、検視現場で何が起こっているのか。日本の「死因究明制度」の問題点を長年取材してきた柳原三佳氏が話を聞いた。
(聞き手/ノンフィクション作家・柳原三佳)
いつ誰が「不条理な出来事」に巻き込まれるか分からない
柳原三佳(以下、柳原) 2020年11月に出版されたご著書『鑑識係の祈り―大阪府警「変死体」事件簿』(若葉文庫)をいっきに読ませていただきました。
村上和郎氏(以下、村上) ありがとうございます。
柳原 「殺人、事故、自殺。遺体の放つ死臭」「危険な死体描写」「衝撃の刑事鑑識ノンフィクション」・・・、オビにはそんなインパクトのあるコピーが数々並んでいましたが、まさにそのとおりで、非常にリアルな情景が描かれていました。収録されている事案はすべて実際に起こった出来事なのですよね。
村上 はい、すべて事実です。私は所轄の捜査部門(刑事や鑑識)として27年つとめ、振り返れば4000件にのぼる異状死の現場に臨場しました。本書はその中でも特に記憶に残った30の事件を、当時の新聞記事などを掘り起こし、故人のプライバシーに配慮しながらまとめたものです。
柳原 私たちは日々、さまざまな事件や事故の報道を目にしていますが、ご著書を読ませていただき、「人の死」には本当にいろいろなかたちがあることを痛感しました。そして、それぞれの現場には、村上さんのように所轄の鑑識係の方々がいち早く駆け付けておられるのだということ、またそのお仕事の内容も初めて具体的に知ることができました。
村上 私としても、この本を通して、警察官が毎日のように異状死の発生現場へ臨場しているのだということを、多くの方に知ってもらいたいという気持ちがありました。

村上和郎〈むらかみ・かずろう〉 元大阪府警察 警部 昭和34(1959)年、大阪府大阪市生まれ。奈良市立一条高等学校卒業。昭和54(1979)年、大阪府警察の巡査を拝命。翌年に配属された枚岡署の警ら課(現・地域課)交番勤務、直轄警察隊を経て、以後は所轄の豊中署、東成署、西成署、布施署、松原署、富田林署の刑事課捜査員や鑑識係として約27年勤務。平成25(2013)年からは吹田署と八尾署の留置管理課をつとめ、平成29(2017)年に健康上の理由で依願退職。在職期間は約38年。現在は飲食店運営会社に勤務。
柳原 この本のカバー(折り返し部分)には、『当直のたびに発見される、変死体の数々――。どろどろに腐敗した遺体であっても、彼は嫌な顔ひとつせず、黙々と捜査を続ける。ときに、目を潤ませながら・・・』。こうも書かれていましたね。
村上 不条理な出来事は、いつ、どのように起こるか、誰にもわかりません。信号待ちをしていて、突然、車に突っ込まれるかもしれないですよね。多くの人の最期の姿を見てきた私は、だからこそ今、この瞬間を大切にしてほしいという気持ちを伝えたいという思いもありました。
柳原 これから読まれる方々のために具体的な事例の紹介は避けますが、村上さんが、産まれた直後に路上に放置されていた赤ちゃんのご遺体を毛布にくるんで抱っこされたシーンは、特に胸に迫りました。
村上 そうですね・・・、何度臨場しても、辛いのはやはり小さなお子さんのケースでしたね。
柳原 この本には目をそむけたくなるような凄惨な現場や、どうすることもできない人間の性が描かれていますが、全編にわたって死者やそのご家族への優しい視点が盛り込まれ、読み進めながら温かい気持ちになれる・・・、そんな不思議な本だと感じました。
誤認検視のリスクとその理由
柳原 私は「死因究明」の問題についても長い間取材を続けてきました。ご遺族の中には、家族の「死因」に納得できない方がかなりおられるんです。過去の取材の中では、全国各地の県警本部に出向いて捜査一課の刑事さんに直接インタビューをしたこともありました。
村上 柳原さんの書かれた著書は、『死因究明?葬られた真実』(講談社)のほか、千葉大の法医学教授と書かれた共著『焼かれる前に語れ』など、読ませていただきました。海外の死因究明制度もいろいろ取材されていましたよね。日本の死因究明制度では誤認検視が起こるのではないかというご指摘、私もその通りだと思います。
柳原 村上さんのご著書の最後に、「検視のリスクを危惧している」というくだりがありましたが、このことを警察官の立場で言ってくださる方は、なかなかいらっしゃらないので驚きました。
村上 現行の検視制度では、現場の状況と遺体の外表からの検視だけで事件性の有無を判断するのですが、まだ皮膚が柔らかい子どもの腹部などに対する暴行や、前例の少ない珍しい薬毒物の中毒死など、遺体の外表にほとんど痕跡が残らない殺人は、実は多数あるんです。まして、所轄の警察官だけで事件性の有無を判断するとなれば、誤認検視の危険性もあります。
柳原 つまり、犯罪が見逃されてしまうわけですね。事件性がないと判断されると、解剖には回らないわけですが、これは順序が逆だと思うんです。本来は解剖や薬毒物検査など医学的な検査を行ったうえで、犯罪性の有無を判断すべきではないでしょうか。
村上 おっしゃるとおりです。でも現実には、検視の業務をおこなう所轄の警察官や、臨場率の向上と誤認検視を防止するために年々増員されている検視調査課の検視官(警察官)は、医師の資格がありません。検視官がいくら警察大学校で2カ月ばかり法医学についての教育を受けたところで、遺体の外表検視だけで判断できるはずがありません。
柳原 検視官は必ず現場に駆け付けるのですか?
村上 大阪府警のケースでいえば、監察医制度の対象外(大阪市以外)にある所轄で事件が発生した場合、所轄の警察官と本部から臨場した検視官が協議します。そして、「事件性」と「解剖」の有無について検視官が判断することになります。

鑑識係として勤務していた当時の村上氏
柳原 事件性が無いと判断されると、どうなりますか。
村上 その後の事件処理は所轄の警察官に引き継がれるため、本来は被留置者の健康管理の為に委嘱している警察医(医師)に、所轄の署長が「遺体検死」(「検視」でない)を要請し、警察医の所見を聞いた所轄の警察官が最終判断をすることになります。
柳原 最終的には警察官に判断が委ねられるのですね。
村上 そうです。事件現場では医師の資格がない警察官が遺体を調べ「事件性」と「解剖」の有無について判断する捜査体制になっていますので、遺体の取り扱いに慣れていない警察官にとっては、それを決定するときに強いストレスが生じることになります。
青酸化合物を使った連続殺人が当初は「事件性なし」とされたことも
柳原 記憶に新しいところでは、筧千佐子という高齢女性による青酸化合物を使った連続殺人が関西で起こりました。被害者は11人ともいわれていますが、彼女の周りの男性が次々に不審な死を遂げていたのに、ほとんどの死が「事件性はない」と判断されてきたわけですよね。
村上 大阪府でも被害者が出ていましたから、あの事件が発覚したときは「自分が見逃したんじゃないか?」と、心配になりました。物言わぬ遺体から「死因」を聞き出すことはできません。そういう意味では、現場に臨場する警察官や検視官は、常にかなりのストレスを抱えていると思います。柳原さんも海外で取材をされていましたが、欧米諸国のような、捜査機関から独立した「メディカル・イグザミナー(ME)」や、「コロナー(医師の資格を持つ検視官)」のような専門職を、日本にもぜひ作ってほしいと思います。
柳原 2013年4月、増加している「異状死体」(病院以外で亡くなった死体)に対応するため、「死因・身元調査法」(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律)が施行され、新しい法律に基づく新法解剖が導入されました。詳細についてはご著書の中で説明しておられますが、この法律によって、死因究明の現場では何か変化はありましたか?
村上 残念ながら現状ではまだまだ不十分だと思います。検視官の増加と共に臨場件数も増えましたが、結局、検視官は医師ではないため、数を増やしても同じなのです。誤認検視をゼロに近づけるためにも、死因究明の専門職や法医学研究所のような専門機関を創設するなど、対策は急務だと思いますね。
柳原 今回のご著書は、過去の事件を回顧されているだけでなく、今の捜査現場が抱える問題点をあぶり出し、この先の制度改正の必要性にまで言及されていて大変意義があると思いました。まさに、4000体という膨大な数の「変死体」を扱ってこられたご経験によるところが大きいのでしょうね。
村上 はい。私はあえて、序章にこう書きました。『この世に殺されてもかまわない命は、ただのひとつもないはずだ。(中略)犯行の痕跡を探すことは、すなわち、被害者の「命の証」を探すことでもある』。この信条を多くの方に伝えていきたいと思います。
柳原 ありがとうございました。